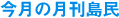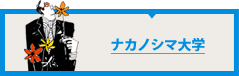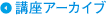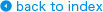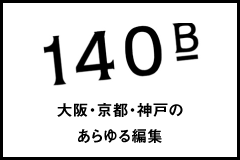セミナーレポート
第6回 2010年3月講座
「仏教がわかれば、落語がわかる!」

大の演芸マニアであり、落語の中の仏教を解説した著書もある釈徹宗先生。仏教系大学を出て入門歴15年、全国各地の寄席やテレビで活躍中の桂文鹿さ ん。『月刊島民』19号の落語特集を飾ってくれたお二人が顔を合わせたナカノシマ大学3月講座のテーマは、ずばり「仏教がわかれば、落語がわかる!」。落 語と仏教の奥深く、興味尽きぬ関係を、釈先生の講義と文鹿さんの口演という豪華二本立てで味わう講座となった。
落語は「いかに人生を生き抜いていくか」の知恵の結晶。
仏教とは、釈先生によれば「苦しみ多い人生をいかに引き受けて生き抜くのかという、人類の知恵の結晶」。そこから生まれた芸能は、舞謡、演劇、浄瑠 璃まで数多い。語り芸の代表が落語だ。「一人の人間が扮装もメーキャップも背景もなしに正座して語り続けるという、世界でも例のない話芸のスタイルは、仏 教のお説教がルーツになっているから」なんだそう。
大衆の人気を集めた説教僧は平安時代からいて、『枕草子』にも出てくるほどだが、噺家はその系譜に連なる。説教の中から笑いの部分を取り出して笑話 集『醒睡笑』をまとめ、「落語の祖」とされる安楽庵策伝は浄土宗の僧侶。江戸時代におそらく初の職業噺家となった京都の露の五郎兵衛も、もとは日蓮宗の僧 だった。「高座」「前座」といった言葉も説教に由来するし、「(客に)受ける」というのは「受け念仏」が語源だという。
その成り立ちからして仏教と不可分な関係にある落語。当然、ネタの中にもその色は濃い。定番ネタの『寿限無』でも、子供の名付けという行為の中に多 くの宗教知識が盛り込まれているし、釈先生がアレンジ台本を手掛けたこともある『お文さま』は、船場の商人たちの熱心な浄土真宗信仰が背景になっている。 「仏教を少し知るだけで、噺の理解度や面白さがまるで違ってくる」と釈先生。といっても仏の教えを有り難がるばかりじゃない。人間の業を笑う落語は、ルー ツである仏法や僧侶も笑いの対象にしてしまうのだ。「原理主義ではこうはいかない。宗教を笑うには、成熟した宗教性と高い文化性が必要なんです」。
落語文化の底流にあるのは、「すべては関係し合って一時的に存在している」という仏教の考え方。倫理的な正しさや「こうあるべき」という枠組みを軽やかに外してみせる落語の特性を、釈先生は、十一面観音像の中で大笑いする「暴悪大笑面」に喩えてみせる。
イマジネーションが、寄席を「宗教的な場」に変える。
そして、落語を楽しむのに最も大切なのは「聞き手のイマジネーション(想像力)」。聴衆はそれぞれ勝手に頭の中で絵を描きながら聞いているものだ が、優れた噺家はその場にいる全員のイメージを一つの像にシンクロさせることができる。それを最大限に引き出したのが三遊亭圓朝や橘家圓喬といった伝説の 名人たち。「そうなると、そこは寄席でありながら宗教的な場になる。イマジネーションを最大限に働かせてこの場を豊かなものにしてください」とは、釈先生 の説く聞き手の心得である。
続いて高座に上がった文鹿さん、まずは仏教ネタの洒落や小話などをたっぷりと披露し、次々と笑いを引き起こす。「釈先生の言ってたのはこういうこと だったのか」と、軽やかに教えてくれた。この日のお題は『淀川』。活け魚を売り物にする魚屋に現れたお坊さんが、殺生を戒め、俎上の魚を買い取るうちに、 どんどん話はエスカレートして…という噺。一瞬「ええっ」というシュールなサゲも、文鹿さんの話術で、笑いとともに着地。最後は本日の講義&口演を振り返 るお二人の対談までオマケについて、120人の受講生たちは、アタマとカラダで落語と仏教の世界を堪能したのだった。
 |
|
 |
|
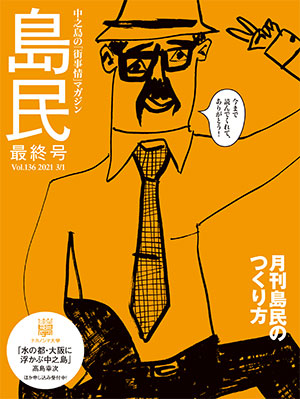
- 島民 最終号(2021年3月号) 「月刊島民のつくり方」
-
いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!