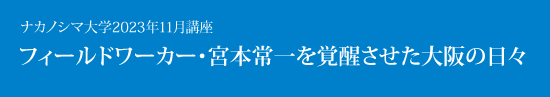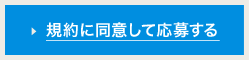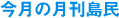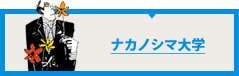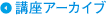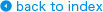20世紀の日本を代表する民俗学者は大阪で、
人から話を聞くおもしろさに目覚めた。
講 師:畑中章宏(民俗学者)
 宮本常一が長屋住まいした釣鐘町界隈(大阪市中央区)
宮本常一が長屋住まいした釣鐘町界隈(大阪市中央区)
 『忘れられた日本人』に登場する、「世間師」から丹念な聞き取りを行った南河内の滝畑(河内長野市)
宮本常一(みやもと・つねいち/1907〜81)は20世紀を代表する民俗学者です。日本列島をくまなく歩き(総歩行距離は地球4周分に相当)、訪れた地域で人びとの暮らしや生き方について丹念な「聞き取り」を行い、『忘れられた日本人』(岩波文庫)などの名著を残した偉大な研究者でした。同時に、その土地の産業が少しでも向上することに労を惜しまない、凄腕の「地域振興コーディネーター」でもありました。そんな宮本の奮闘ぶりをパトロンとして支えたのが渋沢栄一の孫・渋沢敬三(元大蔵大臣・日銀総裁)です。
『忘れられた日本人』に登場する、「世間師」から丹念な聞き取りを行った南河内の滝畑(河内長野市)
宮本常一(みやもと・つねいち/1907〜81)は20世紀を代表する民俗学者です。日本列島をくまなく歩き(総歩行距離は地球4周分に相当)、訪れた地域で人びとの暮らしや生き方について丹念な「聞き取り」を行い、『忘れられた日本人』(岩波文庫)などの名著を残した偉大な研究者でした。同時に、その土地の産業が少しでも向上することに労を惜しまない、凄腕の「地域振興コーディネーター」でもありました。そんな宮本の奮闘ぶりをパトロンとして支えたのが渋沢栄一の孫・渋沢敬三(元大蔵大臣・日銀総裁)です。
瀬戸内海に浮かぶ周防大島(山口県)の農家に生まれた宮本をそこまで動かした原動力とは何だったのか? 実は宮本が15歳の時に島を離れて就職のために出てきた街が大阪だったのです。
「宮本さんが『忘れられた日本人』で発見した寄合民主主義をはじめとする“民俗知”は、民俗学の枠を超えた各界で注目を浴びています。そんな宮本さんの原点が、釣鐘町の長屋、桜宮の逓信講習所、高麗橋の郵便局、天王寺の師範学校、民俗採集をした和泉や河内など、大阪の街や村にあったことはそれほど知られていません。宮本さんは、日本各地を見て歩く際はつねに、大阪を出発点にして庶民と向き合ったのでした」(講師・畑中章宏さん)
 滝畑(河内長野市)にて。宮本常一は民家に設えられた道沿いの石積みも丁寧に観察した
「あるくみるきく」を生涯実践し続けた宮本常一は、若き日に大阪でどんなひとびとに出会って民俗学者への道を歩んでいったのか? 手元のスマホで海外の情報でも瞬時に手に入る時代だからこそ、自分の「生身」を駆使して地域と人に向き合っていった宮本常一の足跡を知ることは、いま大きな意味があるはずです。
滝畑(河内長野市)にて。宮本常一は民家に設えられた道沿いの石積みも丁寧に観察した
「あるくみるきく」を生涯実践し続けた宮本常一は、若き日に大阪でどんなひとびとに出会って民俗学者への道を歩んでいったのか? 手元のスマホで海外の情報でも瞬時に手に入る時代だからこそ、自分の「生身」を駆使して地域と人に向き合っていった宮本常一の足跡を知ることは、いま大きな意味があるはずです。
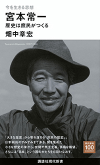
◎当日、大阪府立中之島図書館のミュージアムショップでは、著書『今を生きる思想 宮本常一 歴史は庶民がつくる』(講談社現代新書)などを販売します。
|
畑中章宏(はたなか・あきひろ) 1962年大阪生まれ。災害伝承・民間信仰から、最新の風俗・流行現象まで幅広いテーマに取り組む。著書に『災害と妖怪』(亜紀書房)、『天災と日本人』『廃仏毀釈』(ちくま新書)、『21世紀の民俗学』(KADOKAWA)、『死者の民主主義』(トランスビュー)、『日本疫病図説』(笠間書院)、『五輪と万博』(春秋社)ほか多数。新刊に『今を生きる思想 宮本常一 歴史は庶民がつくる』(講談社現代新書)、『感情の民俗学 泣くことと笑うことの正体を求めて』(イースト・プレス) |

|
| 【開催概要】 | |
|---|---|
| 開催日 | 2023年11月17日(金) |
| 時間 | 18:00〜19:30(開場17:30) |
| 会場 | 大阪府立中之島図書館3階 多目的ホール |
| 講師 | 畑中章宏 |
| 受講料 | 2,000円 |
| 定員 | 50名 ※会場のみの開催です(オンライン受講はありません) |
| 主催 | 大阪府立中之島図書館(指定管理者:ShoPro・長谷工・TRC共同事業体) |
| 企画協力 | ナカノシマ大学事務局(株式会社140B) |
| 【会場】 | |
|
大阪府立中之島図書館 |
|
| ご参加までの 流れ |
|
|---|
ナカノシマ大学応募規約
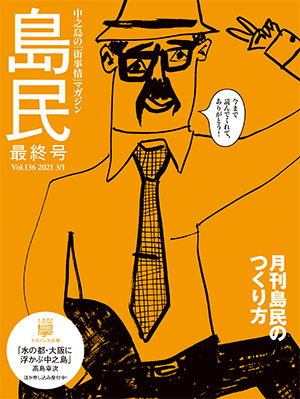
- 島民 最終号(2021年3月号)
「月刊島民のつくり方」 -
いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!