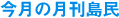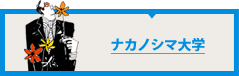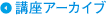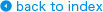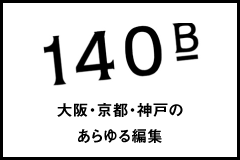セミナーレポート
第16回 2011年1月講座
「大阪の神さん、仏さん part1〈神社編〉」

ナカノシマ大学初のシリーズ企画「大阪の歴史をやり直す」。聞き手である釈徹宗先生が、毎回ゲストを招いて大阪の知られざる顔を解き明かしていく。第2回目となった1月講座では「大阪の神さん、仏さん part1〈神さん編〉」と題し、ゲストに大阪大学招聘教授の高島幸次先生をお招きして、神道と大阪の神社にまつわるあれこれを紹介していった。

まずは高島先生によるプレゼンテーション。神仏を語る前の大前提として、初めに誰かが言い出したことで生まれた「創唱宗教」と、いつ誰からともなく生まれた「民間信仰」の違いや、森とアニミズム/照葉樹林と神道/針葉樹林と天神信仰といった信仰と植生の関係性が説かれた。
さらに大阪にある神社の特徴として、社格の高い神社が多いことや夏祭りの数が多く規模も大きいことなどが挙げられた。また、造幣局の近くに建っていた川崎東照宮についての逸話を紹介。高島先生は、大阪に徳川家康を祀った東照宮があった理由を「豊臣側の街である大阪に、家康を祀って手なずけてやろうと思ったんでしょうね」と分析。参加者の知的好奇心を十分にくすぐり、いよいよ対談へ。

対談は釈先生のこんな質問から始まった。「大阪にはタイガース神社なんてものまであるように、その気になれば何でも祀ることができる。その中で神を高島先生なりに表現するなら?」。すると高島先生は「祠や社のあるなしではなく、人間の弱さに対して何かに頼るとき、それがすでに神なのではないか」と定義した。
さらにご利益や役割も時代・場所によって付け加えられ、変遷していくことを踏まえた上で、「大阪に限って言えば、住吉さんなど海や水にまつわる神さんが多い。現代に生きる我々は生命が海から生まれたことを知っているが、まるで昔の人もそれを知っていたかのよう。偶然かもしれないが、摂津・河内・和泉など海や水に関係した地名も多い」。時間や空間を超えてつながっていくダイナミックな展開に、参加者から驚きと感心の声があがった。
二人の対談はさらに広がりを見せ、日本のように変わらない創唱宗教と変わり続ける民間信仰を一体化させた民族は世界を見渡してもそうおらず、「自らに合うものだけを取り入れて変容させていく、日本人の新しい文化への受け方の上手さが見えてくる」と、釈先生もあらためて感嘆。大阪の神さん論を飛び越え、信仰から見た日本人論にまで発展しかかったところで、今回は残念ながら時間切れ。次回の開催がなんとも楽しみな講義となった。
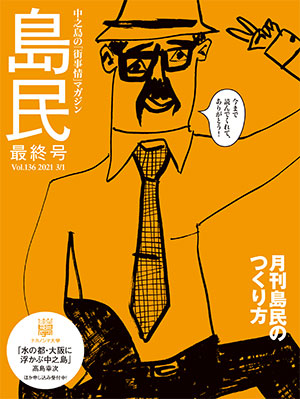
- 島民 最終号(2021年3月号) 「月刊島民のつくり方」
-
いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!